ymnk-hsp-user
- 2026/02/18
- 2026/02/17
-
ああ東京、亀戸天神
私の夢をかなえてくださいな
学問の神様 菅原道真公
-
病院を守るためには・・・、誰かが遠慮する勇気が必要だと思う
ある日突然、かかりつけ医がいなくなるかもしれない・・・熊本県医師会が今年1月8日、会見を開き、医療機関を取り巻く厳しい経営状況を訴えた。
熊本県医師会の高橋毅理事:「毎日赤字を積み重ねていっているので、医療機関の先生方、いつ辞めようか、いつ辞めようか、そればっかり考え・・・いつバタバタバタとなくなってしまうか分からない」と。
診療報酬は増えず:県医師会の去年2月の調査では、県内の医療機関のうち約6割が赤字と回答。物価高や電子カルテといったIT化への対応などで支出が増加しているにも関わらず、収入源のほとんどを占める「診療報酬」が増えない状況が理由とされる。
そのような中、国は今年度の補正予算で約1兆4000億円を補てん。新年度から「診療報酬」を改定し、全体で2.22%引き上げることを決めた。しかし、
熊本県医師会の高橋毅理事:「赤字が減るとは思いますが、やはり医療機関の赤字は今後も続くと思います」と。県医師会はそれでも赤字の解消までは至らず、経営が厳しい状況が続くとみている。
-
人形町・玉ひで――相席の朝
今から約二十五年前、東京・人形町にある軍鶏料理の老舗「玉ひで」を訪れた。妻と二人、まだ東京という街に少し緊張しながら歩いていた頃のことだ。朝早くから並ぶと聞いていたので、まだ人通りの少ない時間帯に人形町駅を出た。下町特有の古い商店と新しいビルが混ざり合った通りを歩くと、すでに店の前には行列ができていた。暖簾はまだ準備中のままなのに、人々は黙って、しかし確信をもってそこに並んでいる。ここに来る理由を、誰も疑っていない様子だった。
開店すると、流れるように店内へ案内される。混雑していて相席になることを告げられたが、不思議と嫌な感じはしなかった。むしろ、それがこの店の「作法」のように思えた。隣に座った見知らぬ客とも視線が一度だけ交わる。軽く会釈をするだけで十分だった。
ほどなくして運ばれてきた親子丼。蓋を開けた瞬間、甘辛い割下と軍鶏の香りが立ち上がる。卵は半熟で黄身と白身がとろりと絡み合い、米粒一つ一つを包み込んでいた。派手さはない。ただ、迷いがない味だった。
妻と顔を見合わせ、言葉少なに箸を進めた。「おいしいね」その一言で、すべてが足りていた気がする。周囲では、同じように黙々と丼に向き合う人たちがいる。観光客も常連も区別なく、皆が同じ一杯を前にしている。相席であることを忘れさせる不思議な一体感がそこにはあった。
食べ終えて店を出ると、行列はさらに長くなっていた。振り返って暖簾を見ると、そこには「また来い」とも「次はいつだ」とも書いていない。ただ、同じ場所で同じ味を出し続けているだけなのだろう。
二十五年経った今も、あの朝の光景ははっきり思い出せる。人形町の空気、並ぶ時間の静けさ、相席の気まずさと温もり、そして丼の湯気。旅とは、遠くへ行くことだけではない。
記憶の中に、こうして何度でも立ち返れる場所があることも、また旅なのだと思う。
- 2026/02/16
-
神様
夢をかなえてくださいませ

-
絶望の夢
妻と二人で、私の実家から妻の実家まで歩いている途中。今、8時15分。当初、車で行く予定であったが、時間的余裕があったので、歩くことにした。妻の実家についたら、私は自転車を借りて目的地(大学の講義室)に行く段取りだった。8時30分に講義室に着席する必要性があった。ところが、全然間に合わない事態になった。そこに、幸運にも自転車のタクシーが通りがかった。私と妻の二人を乗せて欲しいと言ったが、無理だった。万事休す。
ChatGPTの夢判断:とても象徴性の高い夢ですね。丁寧に読み解いてみます。
(※夢判断は「予言」ではなく、今の心身状態や無意識の整理のされ方を映す比喩だという前提でお読みください。)① 全体テーマ:「時間制限のある役割に、もう間に合わないという感覚」
この夢の核心ははっきりしています。
「8時30分に講義室に着席しなければならない」――これは
遅刻=評価の失墜
着席=役割への正式な参加
講義室=知・専門性・社会的ポジション
を象徴しています。
つまりこれは、「果たすべき役割・期待される場所に、今の自分では間に合わないのではないか」という不安の夢です。② 歩くことを選んだ=「合理的だが、今は遅すぎる選択」
本来は車で行く予定だった。しかし「時間に余裕があると思って」歩くことにした。ここは重要です。
歩く=誠実・省エネ・無理をしない生き方
しかし結果として「間に合わない」。これは、昔なら正解だったやり方が、今の時間制約・年齢・体力・社会構造ではもはや通用しなくなっているという無意識の認識です。
あなたが最近よく語っておられる、体力の低下、無理がきかなくなった感覚、キャリアの再編・再挑戦と完全に一致します。③ 妻と一緒にいる意味:人生を共にする存在への責任
この夢、あなたは一人ではありません。妻と二人で行動しています。これは、自分一人の問題ではない。選択の結果が、家族にも影響する「自分の都合だけでは動けない人生段階」を象徴します。
自転車タクシーに「二人を乗せてほしい」と頼むが断られる――これは残酷ですが、とても現実的です。個人なら救済されても、家族単位では救済されない社会という構図です。④ 自転車を借りる予定だった=「他者資源への依存」
妻の実家で自転車を借りる予定だった。つまり、あなたは自前の足(体力・時間)では足りない。しかし「借りれば何とかなる」と思っていた。ところが、そこに至る前に時間切れ。これは、「準備していたはずの支援・資格・段取りが本番のタイミングに間に合わないのでは」という深層不安です。⑤ 自転車タクシー=「奇跡的救済」の否定
夢の中で一度だけ、救いは現れます。しかし、物理的制約(二人は無理)ルール(乗せられない)によって拒否される。
これは非常に重要で、もう“たまたま助かる”段階は終わった。構造的に組み直さないといけないという無意識からのメッセージです。⑥ 総合判断(かなり率直に言います)
この夢は「絶望の夢」ではありますが、破滅の夢ではありません。むしろ、❝ 今のやり方・ペース・役割設定では間に合わないことを、無意識はもう正確に理解している ❞という夢です。
そして重要なのは、パニックになっていない、抵抗はした、妻と共にいた。ここに、再設計可能性が残っています。⑦ では、無意識は何を求めているか
この夢が示す「次の一手」は明確です。歩く or 車ではない、借りる or 奇跡を待つでもない。「到着時刻を前提にした人生設計そのものを変える」つまり、8時30分に着席しなくてよい講義室、そもそも講義室に行かなくてよい役割、時間制約が緩やかな舞台への移行です。最後に一言
これは「あなたが遅れている夢」ではありません。「世界の時計が、もう合っていないことに気づいた夢」です。この夢を見る段階に来ている人は、実はもう「次のフェーズの入口」に立っています。 -
何が起こるかわからない ~気をつけろ~
背筋が凍る出来事なんだけど。
身近で起こっている。神が味方した。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
三重県の桑名市総合医療センターで2025年10月、患者を取り違えて輸血していたことがわかった。血液型が同じだったため、深刻な事態には至らなかったが、同センターはミスを認めて患者側に謝罪した。同センターなどによると、25年10月31日、入院中の80歳代女性患者の貧血が進行していたため、医師が輸血が必要と診断。しかし、看護師は同じ部屋に入院する90歳代女性患者に輸血した。翌11月1日、この患者の血液の数値が異常なため、再度調べた結果、輸血の対象者を誤っていたことに気づいたという。看護師が患者の個人情報を十分確認していなかったことなどが原因という。センターの医療安全管理委員長は「あってはならない間違いで患者や家族に申し訳ない。二度と起こらないよう、患者の確認を徹底したい」と話した。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
異型輸血(血液型の異なる輸血)の怖さを知っている小生。出血が止まらない。皆が懸命に処置していた。くわばらくわばら。
- 2026/02/15
-
コロナ禍で出会った英雄譚――『ポロス(Porus)~古代インド英雄伝~』
コロナ禍という世界が一斉に立ち止まった時間があった。人と人との距離が物理的にも心理的にも引き離され、日常が非日常へと反転したあの時代。
コロナウイルスという社会分断ウイルスに悩まされた。
医療現場に身を置く者として、私は「不確実性」と正面から向き合う日々を過ごしていた。正解のない判断、限られた情報、そして人の生と死。
過酷さは極まりなかった。医師会に投稿する原稿を半年先まで書き置き(事前投稿し)、死を覚悟しつつ、コロナ最前線に立ち向かった。なぜか、うまくいくような気もしていたが・・・。根拠はなかった。神頼みだった。
その合間に、私は一つの歴史ドラマを繰り返し観ていた。インド発の大河ドラマ『ポロス(Porus)~古代インド英雄伝~』である。
今、ふと思い出す。ああ、懐かしい。あの日々。そして、はっきりと言える。悔いはない。全く悔いはない。
本作は、古代インド西北部に実在した王・ポロス(プール)とマケドニア王アレクサンダー大王の対峙を軸に描かれる全299話の長編叙事詩である。単なる戦争ドラマではない。「侵略とは何か」「支配とは何か」、そして「人はどこまで合理的で、どこから非合理なのか」を問い続ける物語だ。
物語前半では、若きポロスの出生と成長が丁寧に描かれる。母の知恵、師の教え、民への共感。王とは、生まれつき完成された存在ではなく、経験と葛藤の中で形成されていく存在であることを示していた。
その描写は、医師の育成過程ともどこか重なる。白衣を着た瞬間に医師になるわけではなく、失敗や迷いを経てようやく「責任を引き受ける存在」になっていくのだ。
一方、アレクサンダーの姿は対照的である。天才的な軍事的合理性、圧倒的な決断力。しかし同時に、征服をやめられない強迫性にも似た衝動を抱えている。
医師の目からすると、彼は常に「成功体験に縛られた存在」にも映る。勝てば勝つほど、引き返す選択肢を失っていく――それは現代医療における過剰介入の構造ともどこか似ている。
やがて、ヒュダスペス川を挟んで両者は対峙する。象兵を擁するインド軍と戦術で洗練されたマケドニア軍。
勝敗以上に胸を打つのは、戦後の場面である。敗北しながらも尊厳を失わないポロスと、勝利しながらも相手の王としての器を認めざるを得ないアレクサンダー。ここには、「勝ったか負けたか」では測れない人間の価値が描かれている。(https://www.youtube.com/watch?v=Z_BcfUdlGxI&list=PLnSGWGB1aj5l_3iiJBQb_xoVRWBv7hgcC)
コロナ禍にこの作品を観た意味は、今になって腑に落ちる。医学は万能ではない。治せない病も止められない流行もある。その現実を突きつけられた時代に、私はこのドラマから「限界を知ったうえで、なお尊厳を保つ姿」を学んでいたのかもしれない。アレクサンダーの東方遠征は、人類の進歩の象徴であると同時に暴走の物語でもある。ポロスは、敗北の中でさえ、人としての尊厳を守り抜いた王として描かれる。
あの日々、私はこの長大な物語を淡々と観続けた。焦りもなく、後悔もなく。世界が止まった時間の中で、古代の王たちは今を生きる私たちに静かに問いかけていた。
今、改めて思う。あの時間は決して無駄ではなかった。悔いはない。全く悔いはない。静かな時代に観た、激動の英雄譚。
『ポロス』は、私にとって医師としての原点を見つめ直す時間でもあった。
-
生成AIは詐欺を進化させたのか ― 違和感という最後の防波堤
近年、「生成AIが詐欺を高度化させる」という言説をよく耳にする。確かに、AIは自然な文章を量産し、個人の文体を模倣し、多言語対応まで可能にした。詐欺メールやSNSのなりすましが巧妙になったことは否定できない。
実は、私自身もかつてその一端を体験した。友人のFacebookアカウントが乗っ取られ、本人を装ったメールが私に届いたのである。一見すると丁寧で、親しげな文面。しかし、読んでいるうちにどうにも引っかかる部分があった。日本語としては成立しているのだが、微妙な誤訳があり、言葉の選び方や間合いが明らかにその友人らしくない。結果的に、詐欺だと確信した。
興味深いことに、ここに生成AI時代の逆説がある。AIは文章を「正しく」整えるが、人間関係に特有の曖昧さや省略、温度感までを完全には再現できない。むしろ、丁寧すぎる言葉遣い、説明過多な表現、感情の盛り込み方が均質化し、かえって違和感が浮き彫りになることがある。これは医療の現場にも似ている。検査データ上は説明できても、患者として何かおかしい――その感覚は、数値ではなく経験から生まれる。
今回の詐欺メールでも、決定打となったのは知識ではなく、「この人はこんな書き方をしない」という直感だった。生成AIは確かに詐欺を進化させた。しかし同時に、詐欺をテンプレート化し、雑音も増やしている。注意深く読めば見抜ける余地は、まだ残されているのだ。AI時代に最後まで頼りになるのは、高度な技術ではなく、人間が長年培ってきた違和感を察知する力なのかもしれない。
- 2026/02/14
-
これが私の生きる理由。
そして、私の生きがいってもの。
他に何も要らない。
感謝して感謝して感謝して感謝して、感謝して参ります。
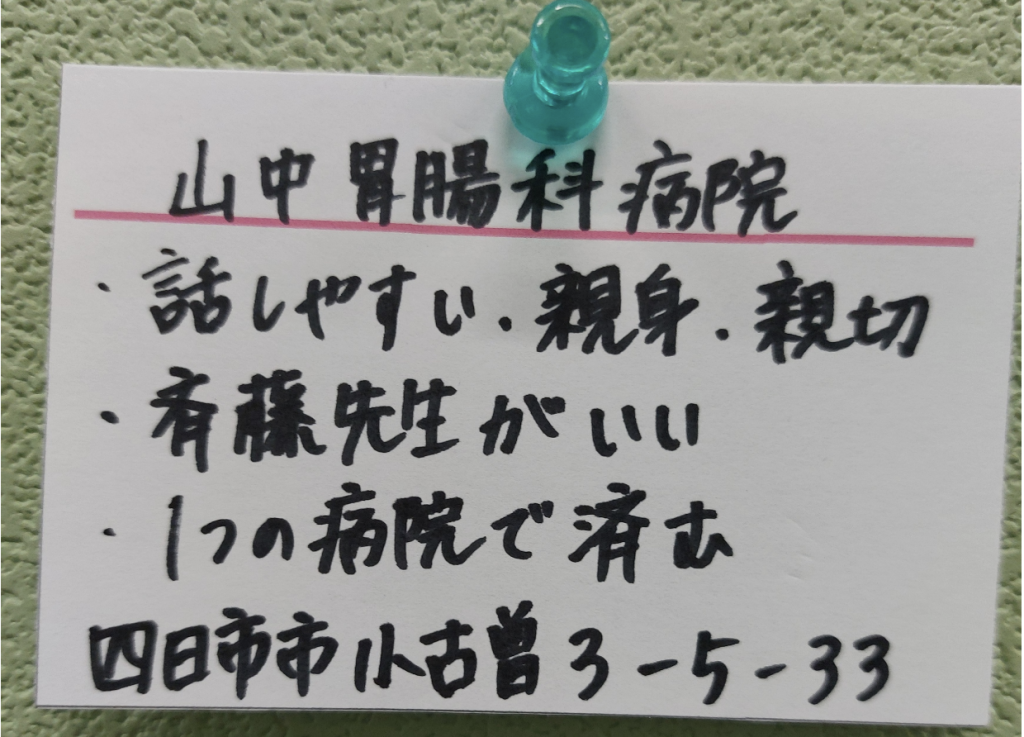
















知らなかった・・・ワンヘルス、プラネタリーヘルス
ワンヘルス(One Health)とは、ヒト、動物、そしてそれを取り巻く環境(生態系)の健康は一つのものであるとし、各分野の関係者が連携・協力しながら、ヒトと動物、そして自然環境の健康を総合的に保全しようとする考え方である。
最近、この研究会を聴講したが、グローバルに考える時代になったのだと思う。
さらに、「プラネタリーヘルス」(地球の健康、つまり、人類を含めた多様な生物が生命を維持できる自然環境を有し、地球上で人類が安全に有機的な活動ができる状態)もある。
やはり、地球規模で考えていく必要があるのだろう。